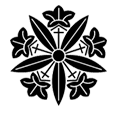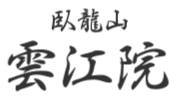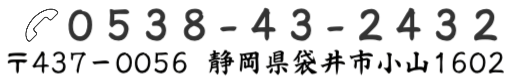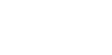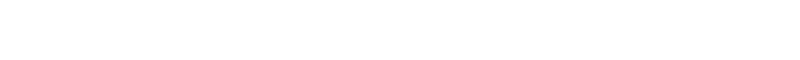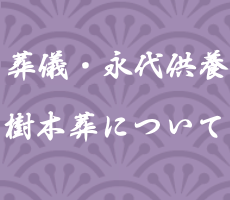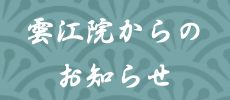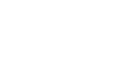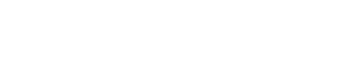今からおよそ450年前の天正5年(1577年5月)、可睡斎13世 士峯宋山大和尚様により雲江院が正式に開かれました。
慶長8年(1630年)3月12日、将軍徳川家光公より朱印高15石(1町7反8畝)を拝戴されました。
宝暦年間(1751~1763年)に徳川幕府から可睡斎後見役寺に列せられました。
慶長9年(1604年)7月1日に火災により堂宇伽藍が悉く焼け、同年客殿を再建。
明治8年(1875年)に朱印地等は明治新政府に返還されました。
昭和19年(1944年)、東南海地震の為に、堂宇伽藍が全て倒壊。
戦時中の為に復興もままならず、庫裡・位牌堂を仮設していましたが、昭和34年に旧豊岡村野部の保安寺の古い本堂を購入し、利用しました。
その後、書院・本堂・庫裡の新築・改築を、当時の住職と檀信徒が力を合せて行い、現在の雲江院伽藍へと繋がっています。
- 開創
- 伝 天正5年(1577年)5月
- 本尊
- 十一面観世音菩薩
- 宗名
- 曹洞宗(禅宗)
- 本山
- 福井県 大本山永平寺
- 神奈川県 大本山總持寺
- 開山
- 士峯宋山(しほうそうさん)大和尚